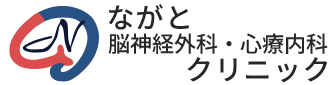脳神経外科に
ついてNeurosurgery
脳神経外科では、脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)などの脳血管疾患、頭部や脊椎・脊髄の異常、パーキンソン病やてんかんなどを脳神経外科専門医が診察します。頭痛やめまいなど、脳に関する症状全般にも対応しています。
また、脳の病気と関わりの深い高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病の管理も行い、脳の健康を支えています。
心の不調がある方には心療内科と連携し、心と身体の両面からサポートできる体制を整えています。

このような症状は
ご相談ください
- 頭痛がする
- 手足や顔のまひがある
- めまいがする
- しびれやふるえがある
- 耳鳴りがしている
- うまく話せない
脳卒中
(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)
脳卒中は、脳の血管が破れたり詰まったりして血流が止まり、身体に障害が現れる病気で、「脳梗塞」と「脳出血(脳内出血・くも膜下出血)」に分けられます。
特に脳梗塞は心臓病や動脈硬化と関わりが深く、高血圧、脂質や糖の代謝異常、心房細動などが原因となります。
さらに過食や飲酒、運動不足、ストレスなどの生活習慣にも影響します。なかでも高血圧は発症に大きく関与するため、日常的に血圧を意識した生活が大切です。

- 片側の手や足、顔の半分に力が入らなくなったり、しびれたりする
- うまく話せなくなったり、言葉が出てこなかったり、人の話が理解しづらい
- 筋力はあるのに立ち上がれなかったり、うまく歩けなかったりふらつく
- 視野の半分が見えにくくなったり、突然短い時間だけ見えなくなったりする
- 突然、これまでにないような激しい頭痛が起こる
こうした症状が出たときは、できるだけ早めに医療機関を受診してください。
脳卒中の種類
脳梗塞
脳梗塞は、脳への血流が止まることで脳の組織が損傷を受ける病気です。
高血圧や脂質異常症、糖尿病などによる動脈硬化、不整脈によって心臓でできた血のかたまりが脳の血管を詰まらせることなどが原因になります。片側の手足や顔のまひ、ろれつが回らない、言葉が出にくいなどの症状が突然現れます。
早期に治療を始めることで、薬やカテーテルによって血のかたまりを取り除き、後遺症を軽くできる可能性があります。
脳出血
脳出血は、脳の細い血管が破れて脳の中に出血が起こる病気です。血液がたまると、その周囲の脳の組織が傷つき、出血した場所に応じて手足のまひや意識障害などの症状が現れます。出血が広がると命に関わることもあります。原因として多いのは高血圧で、動脈硬化により血管の壁が破れやすくなることが背景にあります。
減塩などの普及で死亡率は減っていますが、生活習慣の変化や高齢化、薬の影響などにより注意が必要な病気です。
くも膜下出血
くも膜下出血は、脳の表面にある「くも膜下腔」に出血が起こる病気で、多くは脳の血管のふくらみ(脳動脈瘤)が破れることで発症します。40代後半から60代に多く、命に関わることがあります。
突然の激しい頭痛が特徴で、バットで殴られたような痛みと表現されます。重い場合は意識がもうろうとしたり、意識を失ったりすることもあります。再出血の危険があるため、早期に原因の血管を見つけて対応することが大切です。
検査・治療について
問診・診察・採血・頭部のMRI検査などを行います。
治療は点滴や内服が中心となります。
※症状や身体の状態に応じて、処置の内容は変わります。
血管内治療が必要な場合は、速やかに専門の医療機関を紹介します。
片頭痛
片頭痛は特別な病気が原因ではなく、多くの方が経験する頭痛のひとつです。
前兆として視界に光が見えたり、感覚が鈍くなったりした後、片側または両側に脈打つような痛みが数時間から数日にわたって続くことがあります。
吐き気を伴ったり、光や音に敏感になったりするため、日常生活に支障をきたすこともあります。当院では症状を和らげる薬の治療に加え、予防のための注射治療にも対応しています。

- 視界にキラキラやギザギザの光が現れ、頭痛が始まる
- ズキズキと脈打つような痛みが、片側または両側に現れる
- 普段は気にならない光・音・臭いを不快と感じる
- 階段昇降など日常的な動作によって頭痛が増強する
※日常生活に影響が出ていると感じたら、我慢せずに早めにご相談ください。
治療について
治療は、急に起こる頭痛(急性期治療)への対応と、くり返す頭痛を減らす治療(予防療法)に分けられます。
- 発作を抑える内服薬(頭痛が起きたときに使います)
- 発作を予防する内服薬(毎日服用します)
- 発作を予防する注射薬(月に1回などの間隔で皮下に注射します)
片頭痛の回数や程度、日常生活への影響などをもとに診断し、治療方法を提案します。
保険適用で予防注射療法を受けるには一定の条件があるため、詳しくは医師にご相談ください。
脳腫瘍
脳腫瘍は、頭の中の圧力が高まることで朝方の頭痛や吐き気を引き起こします。進行すると意識障害を引き起こすこともあります。また、腫瘍の位置によっては半身のまひ、言葉が出にくくなること、視力の変化なども見られます。
さらに、てんかん発作が起こることも多く、部分的なけいれんから全身に広がる場合もあります。治療前後にも発作が起こる可能性があるため、予防的に薬を使用することが一般的です。発作後は一定期間、車の運転を控える必要があります。

- 慢性的な頭痛がある
- 原因不明の吐き気や嘔吐をする
- 見えにくさや視野の異常がある
- 半身のまひや言語障害がある
- めまいや耳鳴りがする
検査・治療について
MRIやCTなどの画像検査にて診断を行います。
その結果をもとに治療方針を検討します。
どのような脳腫瘍でも、基本的には腫瘍をできる限り取り除くことが治療の中心になります。
手術が必要な場合は、専門の医療機関をご紹介し、速やかに対応できるように進めていきます。
めまい症
めまいには、回転するように感じる回転性めまい、不安定でふらつく動揺性めまい、視界が暗くなる失神前駆症状、物が二重に見える複視など、さまざまな種類があります。多くは内耳の異常によりますが、脳卒中や心臓の病気が原因となることも少なくありません。
特に、激しい頭痛、ろれつの障害、手足のしびれや脱力、意識の変化を伴う場合は脳血管障害の可能性があり、早急な受診が必要です。耳鳴りや難聴があれば内耳性を疑いますが、耳症状がなくても中枢性のめまいのことがあります。
脳神経外科ではMRIやCTによって脳や血管の異常を確認し、全身の状態も含めて診断・治療を行います。

- 自分や周囲が回る感じがする
- 不安定なふらつきがある
- ものが二重に見える
- 動悸や吐き気がある
検査・治療について
問診・診察・採血に加え、必要に応じてMRIやCTで脳や血管の異常を確認します。
治療は点滴や内服が中心となります。
原因によってはリハビリが必要になる場合があります。
※症状や身体の状態に応じて、処置の内容は変わります。
血管内治療が必要な場合は、速やかに専門の医療機関を紹介します。